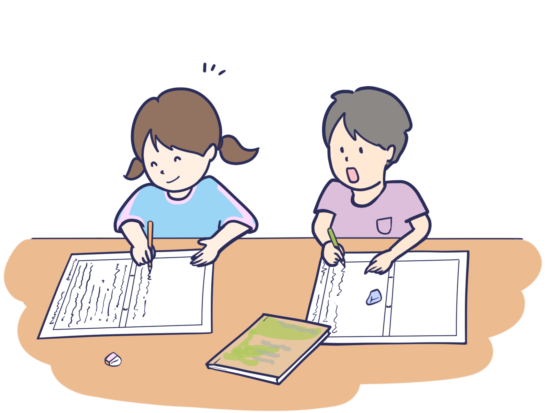小学生夏休みの宿題といえば「読書感想文」ですね!
「読書感想文を書いてね」と言われて、うちの子は鉛筆を持ったまま固まってしまった…。そんな経験、ありませんか?
小学1年生にとって、「感想を文章にする」というのは、まだまだ難しいこと。「なにを書けばいいの?」「どうやって書き出せばいいの?」と、子どもが悩んでしまうのは自然なことです。
実際にまだ低学年では授業で読書感想文の書き方は習わないそうです。本を読んで原稿用紙数枚に感想を書いていくというのは大人でも簡単とはいえませんよね。
この記事では、「小1の子どもが読書感想文を書けないのはなぜ?」という疑問にくわえ、感想文を書くときのステップや構成、書き出しのコツ、親ができるサポートのしかたまで、やさしく解説します。
なぜ小1の子どもは読書感想文が書けないの?原因を知ろう
小学校1年生の子どもが読書感想文を前にして手が止まってしまうのは、よくあることです。でも「どうして書けないのか?」という原因を知れば、サポートの方法が見えてきます。
この章では、「感想ってなに?」「どう書けばいいの?」と戸惑う理由や、言葉の力・経験の不足がどう影響しているのかをやさしく解説。つまずくポイントが分かれば、無理なく書ける道が見えてきます。
「感想って何を書くの?」と子どもが思う理由
小学1年生の子どもにとって、「感想を書いてごらん」と言われても、何をどう書けばいいのかピンときません。
本を読んでも「○○くんがでてきた」「○○をした」など、出来事を説明して終わってしまうことが多いのはそのためです。
これは、子どもが「感想とは、自分の気持ちや考えを書くこと」だとまだ理解できていないからです。
気持ちを言葉にする経験も少なく、「すごかった」「おもしろかった」で止まってしまうのは自然なことです。
さらに、学校でも「読書感想文の型」や「例文」の指導がほとんどなく、自分の気持ちを自由に言葉にする訓練がされていないのが実情です。
子どもたちは“何を書いてもいい”という自由さのなかで、逆に迷い、書けなくなってしまうこともあります。
まずは、「どこが楽しかった?」「びっくりした場面はあった?」など、日常の会話の中で少しずつ気持ちを引き出してあげましょう。
“自分がどう思ったか”に意識を向ける練習を重ねることで、感想文のハードルも下がっていきます。
・この本を読んで、○○くんが○○をがんばっているのがすごいと思いました。
・○○ちゃんがさびしくなったところが、わたしもさびしくなりました。
小学1年生がつまずきやすい読書感想文の“ポイント”とは?
読書感想文でつまずく理由は、いくつかあります。
まずは「何を書いていいか分からない」こと。子どもは「正解」を探しがちなので、「自由に書いていいよ」と言われると困ってしまうのです。
また、本の内容をうまく思い出せなかったり、「どこが大事か」を判断するのも難しい時期です。
さらに、「話す」ことはできても、それを「書く」ことにまだ慣れていないため、手が止まってしまうのもよくあることです。
読書感想文は「読解」だけでなく、「表現」「構成」「自分の気持ちを認識する力」がすべて求められる複雑な作業であることを、親も理解してあげる必要があります。
一見すると簡単そうに見える読書感想文ですが、実は複数の力を同時に使わなければならないため、
小学1年生にはとてもハードルが高いのです。
大切なのは、「どの場面が心に残ったか」「なぜそう思ったか」を一緒に考えること。話しながら整理してから、書く流れにすると、子どもも安心して取り組めます。
・○○くんがなきそうになっているとき、わたしもなきそうになりました。
・○○をがんばるところを見て、わたしも○○をがんばろうと思いました。
「うまく書けない」原因は“経験不足”と“語彙力”
「うまく書けない」と感じている子どもの多くは、感情を表す言葉がまだ少ない状態です。
たとえば「うれしい」「おもしろい」などの簡単な言葉しか使えず、それ以上の気持ちをどう言えばいいのか分かりません。
簡単な表現は知っていても、それ以上の言葉を知らないために、自分の気持ちを適切に表現できず、文が単調になりがちです。
また、小1の子どもには、本で読んだ出来事と「自分の体験」を結びつける力もまだ育っている途中です。だから、書こうと思っても、「どう書けばいいか分からない…」と困ってしまうのです。
「おもしろいね。どうしてそう思ったの?」「どのへんがすごかった?」と、言葉を増やす会話を重ねていくことで、自然と表現が広がっていきます。
・○○をしているところを読んで、わたしも○○したときを思い出しました。
・○○くんが○○をがんばって、すごいなと思いました。わたしも○○をしてみたいです。
読書感想文に適した本とは?

最初に子どもがつまずきやすいのが「本選び」です。
感想文に向いている本を選ばなきゃ、と親御さんが一生懸命になる気持ちはよく分かります。ですが、感想文を書くためのコツは、実は「正解の本を探すこと」ではなく、「子どもが自分で選ぶこと」にあります。
おすすめなのは、本屋さんや図書館で、子ども自身に自由に選ばせてあげること。「これ、読んでみたい!」と手に取った本は、それだけで子どもにとって心が動いた証拠です。内容が難しくなく、最後まで読み切れる本であれば十分に感想文の題材になります。
たとえば、楽しいテレビ番組を見たあと「ねえ、あれ見た?」と友達に話したくなるように、子どもも「この本、おもしろかったよ!」と誰かに伝えたくなるときがあります。そういう気持ちが、自然な感想につながるのです。
つまり、「感想文に適した本」とは、子どもが心から「おもしろい」「読んでよかった」と思えた一冊。親が選ぶ“書きやすい本”よりも、子どもが「好き」と思えた本のほうが、感想はずっと書きやすくなるのです。
読書感想文の書き方 小1でもできるステップと手順
文章を書くことに慣れていない小1の子には、「書きなさい」よりも「話してごらん」が近道です。
この章では、読む→話す→書くのステップや、子どもらしい言葉をそのまま活かすコツを紹介。焦らずゆっくり進めることで、子どもが自分の気持ちを言葉にできるようになります。
感想文の第一歩に悩む親御さんにとって、実践しやすい手順がここにあります。
読む → 話す → 書くの順で進める
読書感想文を書くときに、いきなり「さあ、書こう!」とするのは、小1の子にとってはとても難しいこと。まずは「読む → 話す → 書く」というステップを意識してあげましょう。
本を読み終えたらすぐに書かせるのではなく、「どこが楽しかった?」「だれが好きだった?」と会話を通して、感じたことを言葉に出させてみてください。
話す中で、気持ちや印象がはっきりしてきます。それをメモしておけば、あとで感想文にしやすくなります。
例文
「いちばんおもしろかったのは〇〇が△△をしたところです。わたしもあんなことをしてみたいと思いました。」
NG例
「〇〇はたのしかったです。〇〇はたのしかったです。」(くり返しが多く、理由や気持ちが書かれていない)
ポイント
感想文の基本は「読んだ→感じた→書いた」という順番を守ること。すぐに書こうとせず、話す時間をしっかり取ってから書き始めるとスムーズです。
焦らず「話し言葉」から文章へ
感想文と聞くと、「ちゃんとした書き言葉で書かないと」と思いがちですが、小学1年生はまだ書く練習の途中段階。
最初は話し言葉でも大丈夫です。「たのしかった」「びっくりした」「すごい!」など、普段の口調がそのまま感想文の土台になります。
子どもが自然に話した言葉を否定せず、「どうしてそう思ったの?」「どのへんがすごかった?」と一歩深掘りすることで、文章がふくらみます。
例文
「〇〇が△△をがんばっていて、すごいなと思いました。わたしもピアノのれんしゅうをがんばりたいです。」
NG例
「おもしろかったです。おしまい。」(気持ちはあるけれど、内容が伝わりにくい)
ポイント
“正しい文”にしようとするより、“伝えたい気持ち”を大切に。話し言葉から始めることで、書くことがぐんと身近になります。
子どもの言葉をメモして残すとスムーズに
子どもが本の感想を口にしているとき、親がそれを聞き流さず、メモしておくととても助かります。
話しているときは思いがあふれていても、いざ書こうとすると忘れてしまうことも多いからです。
子どもは意外と豊かな感情表現をしているもの。「かわいそうだった」「あんなのこわいよね」「ぼくもあったよ」など、話の中にこそ本音や感想のヒントが詰まっています。
例文
「〇〇がにげたところで、ドキドキしました。ぼくもまいごになったことがあるので、こわかったきもちがわかります。」
NG例
「なにもおもいませんでした。」(せっかく感じたことを思い出せないと、空白になりがち)
ポイント
会話の中に出てきた子どもの“言葉のかけら”を残しておけば、あとから感想文にスムーズにつなげられます。書く材料を「その場で集める」ことがカギです。
小1でも書ける!読書感想文のカンタンな構成・組み立て方
感想文には、読み手が分かりやすくなる基本の「型」があります。はじめ・なか・おわりの3つのブロックに分けて考えれば、子どもでも整理しながら書くことが可能です。感情や気づきを盛り込みやすくなる構成例とともに、書きやすいパターンをご紹介します。
【はじめ】本を読んだきっかけ
感想文の最初は「読もうと思った理由」や「本を選んだきっかけ」から書くとスムーズです。これは、まだ文章に慣れていない小1の子にとって、気持ちを整理しやすい入り口になります。
「誰かに勧められた」としてもどうしてその本に自分も興味を持てたのか、というようにそこで自分の考えを書いていくといいでしょう。
例文
「この本は、えを見てたのしそうだとおもって、えらびました。」
「学校のせんせいにすすめられてよみました。」
NG例
「この本をよみました。おもしろかったです。」(いきなり感想に入ってしまい、話の流れがつかみにくい)
ポイント
「なぜこの本を手に取ったの?」という会話から始めると、自然な書き出しにつながります。
【なか】読んで感じたこと
感想文の「なか」の部分は、いちばん大事な“気持ち”を書くところです。
「印象に残った場面」や「心が動いたところ」を中心に思い出してみましょう。「びっくりした」「うれしかった」「かなしかった」など、気持ちが動いたところがあれば、そこが“書きやすいポイント”になります。
ただし、ここでよくあるのが「本のあらすじを長く書いてしまう」こと。感想文なので、物語の流れをくわしく説明する必要はありません。もし本の内容を少し伝えたい場合は、感想につなげるための簡単な説明だけでOKです。
このように、ほんの数行で背景を伝えつつ、すぐに自分の気持ちにつなげるのがコツです。
例文
「ライオンがうそをついてしまって、あとであやまったところがすごいと思いました。」
「わたしもお友だちにうそをついたことがあるので、勇気を出してあやまったのがすごいと思いました。」
NG例
「ライオンが森にすんでいて、ある日うそをついて、動物たちが怒って、あとであやまりました。そして友だちになりました。」
※ただのストーリー説明になってしまい、「どう思ったか」が伝わりません。
ポイント
- 「何が心に残ったか」を先に考える
- あらすじは必要最小限でOK(1~2文)
- 感情(うれしい・かなしい・すごい)を表す言葉を意識する
【おわり】心に残ったこと・これからどうしたいか
「おわり」の部分では、読んだ後に思ったことや、これからの自分にどう生かしたいかをまとめましょう。
たとえば、登場人物の行動から学んだこと、これからやってみたいこと、自分の考えが変わったことなどが書けると、とても立派な感想文になります。
ここでも難しく考える必要はありません。子どもらしい素直な感想が一番です。
「わたしも○○してみたい」「○○ってすてきだなと思った」など、前向きな一言があると読後感がよくなります。
例文
「〇〇をよんで、あいさつをだいじにしたいとおもいました。わたしもあさ、げんきにあいさつしたいです。」
NG例
「これでおわります。」
※あっさり終わってしまい、何が心に残ったのかが伝わりません。
ポイント
- まとめやすい気持ちで終わらせる
- 「今の気持ち」や「これから」の気持ちを書く
- 前向きで自然な言葉がベスト
感想文の書き出しが難しい!小1でも書ける言葉のヒント
書き出しで悩んでしまうのは、大人でも同じ。小1の子どもが「どう始めたらいいの?」と迷っているときは、気持ちを引き出すちょっとした質問が助けになります。
この章では、導入文のヒントや「○○と思いました」以外の言い回し、自然な一文を引き出す会話の例などを紹介。子どもがスッと書き始められる工夫が満載です。
読み始めの「導入文」はどうすればいい?
感想文で一番むずかしいのは、最初の一文を書くこと。小1の子どもにとって、「何から書けばいいの?」と戸惑うのは当然です。とくに“導入文”では、「いきなり感想を書かなきゃ」と思うと手が止まってしまいがちです。
始め方の“パターン”「本のタイトルを書く」「登場人物を紹介する」「読んだ理由を書く」などを教えてあげましょう。「○○という本をよみました」「○○くんが出てくるお話です」など、書き出しはシンプルで大丈夫です。
例文
・「この本をよんで、とてもたのしいきもちになりました。」
・「○○というおはなしの○○くんががんばっていて、すごいなとおもいました。」
NG例
・「かんそうぶんをかきます。」(→あいさつのような書き出しは、感想が始まっていない印象に)
・「わかりません。」(→困っている気持ちは伝わりますが、書き出しとしては不向きです)
ポイント
書き出しは“説明”でよいと伝えると、子どもは気が楽になります。そして「なにが一番心にのこった?」と親が問いかけてみると、子どもは書くきっかけをつかみやすくなります。
会話の中から「はじめの一文」を引き出すのがコツです。
「○○と思いました」だけじゃない!感想の書き出し例
「○○と思いました」は感想文の定番フレーズですが、毎回それだけでは表現が単調になってしまいます。子どもが「おもしろかった」「うれしかった」などの感情を伝えるには、気持ちのバリエーションと言葉のヒントが必要です。
いろいろな感情の言葉を教えてあげると、「そうそう!そんな気持ちだった!」と反応が返ってくることがあります。そこから文章がふくらみ、子どもらしい感想文につながっていきます。
・「○○くんがまけないでがんばっているところをよんで、じぶんもやってみたいとおもいました。」
・「○○がかわいそうで、よんでいてかなしくなりました。」
・「○○のセリフがかっこよくて、わたしもまねしてみたくなりました。」
NG例
・「おもしろかったです。おもしろかったです。」(→同じ言葉のくり返しは内容が伝わりにくくなります)
ポイント
「どうしてそう思ったの?」「そのとき、どんな気持ちになった?」などの質問を重ねてみましょう。気持ちの“理由”を言葉にできれば、感想文に深みが出てきます。
自然な「はじめの一文」を引き出す“質問”とは?
感想文のはじまりに困っているときは、子どもに「問いかけ」をしてあげるのがいちばん効果的です。「どんなお話だった?」「どこが好きだった?」といった具体的な質問で、思い出しやすくなります。
このとき注意したいのは、「これを書きなさい」と指示するのではなく、「○○と思った?」「○○ってすごいね」と一緒に考える姿勢を見せること。子どもは、自分の気持ちを受け止めてもらえると、自然に言葉が出てきます。
・「○○くんがまけないでがんばっているところをよんで、じぶんもやってみたいとおもいました。」
・「○○がかわいそうで、よんでいてかなしくなりました。」
・「○○のセリフがかっこよくて、わたしもまねしてみたくなりました。」
NG例
・「おもしろかったです。おもしろかったです。」(→同じ言葉のくり返しは内容が伝わりにくくなります)
ポイント
親の問いかけがヒントになります。「○○くんががんばってたね。どんな気もちだったと思う?」など、感情によりそった質問を意識してみてください。
まとめ
小1の子どもが読書感想文でつまずくのは、ごく自然なことです。
大切なのは、「どうして書けないのか?」を親が理解し、書く前の会話や構成の工夫を通して、子どもが自分の言葉を見つけやすくしてあげること。
読む→話す→書くという順番や、「はじめ・なか・おわり」のシンプルな構成を知るだけでも、ずっと書きやすくなります。
無理に文章にしようとせず、まずは話すことから。「うんうん、それで?」と受け止めるやりとりが、子どもの表現力を育てていきます。親子で一緒に取り組むことで、初めての感想文もきっと楽しい体験になりますよ。
▼こちらの記事もどうぞ▼