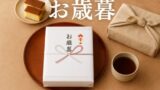贈り物って、選ぶ楽しさもありますが、マナーやタブーを知らずに渡すと意外と失礼になってしまうこともありますよね。
どんな品を贈るかはもちろん大切ですが、渡すタイミングや方法、相手に合わせた配慮も重要です。
この記事では、贈る前に知っておきたいマナーや避けるべき品、スマートに渡すコツまで、実例を交えてわかりやすく解説します。これを読めば、どんなシーンでも安心して贈り物ができます。
贈り物を贈る前に知っておきたい基本マナー
贈り物は相手への気持ちを形にするものですが、マナーを知らずに渡すと印象を損ねることもあります。
包装の仕方や渡すタイミング、言葉遣いなど、基本的なマナーを押さえておくことが大切です。
ここでは、贈る前に知っておきたい注意点と心遣いのポイントを具体例とともにわかりやすく解説します。
贈り物を贈るタイミング
贈るタイミングは、相手に与える印象を大きく左右します。結婚祝いは入籍後1か月以内、出産祝いは生後1か月前後、お見舞いは入院中に贈るのが一般的な目安です。
早すぎると相手が準備できていなかったり、かえって負担になることもありますし、遅すぎると「気遣いが足りない」と感じさせてしまうこともあります。
また、お歳暮やお中元のような季節の贈り物も、相手の生活リズムや職場の慣例を考慮するとより喜ばれます。
ポイントは、相手の状況やスケジュールを意識して、負担にならないタイミングで渡すこと。こうすることで、贈る側の思いやりが自然に伝わり、気遣い上手な印象を与えられます。
贈り物の渡し方のマナー
贈り物は、渡し方ひとつで印象が大きく変わるものです。直接手渡しする場合は、笑顔で一言添えるだけでも心遣いが伝わります。
郵送する場合は、包装を丁寧に整え、のしやメッセージカードを添えることでより印象が良くなります。
特に目上の方には、包み方やのしの書き方をきちんと意識することが重要です。さらに、手渡しと郵送を組み合わせる場合は、事前に連絡を入れたり、相手の都合に合わせて届く日を調整したりすると、スマートな印象になります。
ちょっとした配慮が、贈る側の丁寧さや誠意を伝えるポイントになり、受け取る側も安心して受け取れます。
贈るときに注意したい“語呂合わせ”や“連想”ギフト
日本の贈り物文化には、昔から“言葉遊び”や“イメージ”に由来するタブーがあります。代表的なのは「櫛(くし)」。これは“苦(く)”や“死(し)”を連想させるため、お祝い事にはNG。また、刃物類(包丁やハサミ)も「縁を切る」と考えられるので、結婚祝いなどには避けられます。
花を贈るときも要注意。白い花や菊は弔事のイメージが強いので、誕生日やお祝いの場では避けるのが無難です。逆に、赤いバラを病気見舞いに持っていくのもNG。「血」を連想させるためですね。
こうしたタブーは地域や世代で差がありますが、知らないと失礼になることも。迷ったときは、同じ状況で一般的に贈られているものを調べるか、カジュアルに「こういうものって大丈夫かな?」と相手に確認しておくと、気まずさを防げます。
気持ちを込めることが一番大事ですが、ちょっとした配慮で印象はグッと良くなりますよ。
これは避けたい!贈り物のタブー

贈り物には、思わぬ印象を与えてしまう品があります。足元に関わる靴やスリッパ、割れ物、刃物、強い香りのものは、場面によっては失礼にあたることも。
結婚祝いやお見舞いなど、シーンに応じたマナーを意識することが大切です。ここでは、避けるべき具体例や理由をわかりやすく解説し、安心して贈れる選び方を紹介します。
避けるべき品物とその理由
贈り物を選ぶときには、相手に喜ばれるかどうかだけでなく、マナーとして避けるべき品物にも注意することが大切です。
まず代表的なのは刃物類です。包丁やナイフは「縁を切る」という意味があり、結婚祝いなどのハッピーな場では不向きです。
さらに、ガラスや陶器など割れやすいものも、割れること=別れや壊れるイメージを連想させるため、目上の方やあまり親しくない相手には避けた方が安心です。
また、靴やスリッパ、靴下などの足元関連の品も「踏みつける」といった印象があり、上司や年配の方にはふさわしくありません。
加えて、ハンカチは「涙を拭く」と連想されることがありますが、実はハンカチは漢字で「手巾(てぎれ)」と書くのです。これは「縁を切る」という意味になるので、お見舞いや別れの場では控えた方が無難です。
そして旅行先で選びがちなのがその土地産である日本茶。日本茶は一般的に弔事に使われる品物です。とても可愛くパッケージされていて思わず買いたくなる品物ですよね。でもお茶を買うときは自分用にしておきましょう。贈り物には避けるほうが無難です。
これらは見た目や値段だけで判断せず、文化的な意味や相手に与える印象まで考えて選ぶことが、失礼のない贈り物選びの基本です。
相手を“下に見る印象”を与えてしまうもの
贈り物には、思わぬ印象を与えてしまうものがあります。特に目上の方やビジネスシーンでは注意が必要です。
たとえば、靴やスリッパ、靴下など足元に関わる品は「踏みつける」といったイメージを持たれやすく、相手に下に見られている印象を与えることがあります。
また、筆記用具や時計、バッグといった品も、相手に「もっと働きなさい」「勤勉であれ」といった圧力を感じさせる場合があり、敬意を示す贈り物としては避けたほうが無難です。
さらに、香りの強いアロマや派手すぎるデザインの小物も、好みや価値観が合わないと不快感につながることがあります。
贈り物を選ぶ際は、相手の立場や性格、関係性を想像しながら、受け取ったときに不快な印象を与えないかを基準にすると、失礼のない心遣いが伝わります。
地域や宗教によるNGギフトの違い
贈り物のタブーは、地域や宗教の文化によっても異なります。例えば、関西では包丁やハサミなどの刃物を贈ることは「縁を切る」と捉えられ避けられますが、地域によっては「未来を切り開く」という縁起物としてポジティブに受け取られる場合もあります。
また、宗教的背景も重要です。イスラム教では豚由来の食品やアルコール、ヒンドゥー教では牛肉を含む食品は贈れません。仏教では四や九の数字を避けることがあり、仏事と誤解されやすい品も注意が必要です。
贈る相手の文化や信仰を理解していれば、意図せず失礼な印象を与えることを防げます。贈る前に、軽くリサーチするだけでも、より安心して喜ばれる贈り物を選べます。
シーン別に気をつけたい贈り物のタブー
結婚祝いや新築祝い、お中元・お歳暮、お見舞いなど、贈るシーンによって避けるべき品物があります。割れやすいものや火を連想させるもの、縁起の悪い数字などは特に注意が必要です。
ここでは、各シーンごとのタブーを具体例と理由を交えて紹介し、安心して贈れる選び方を解説します
結婚祝いで避けたいもの
結婚祝いで贈り物を選ぶ際には、縁起や意味を意識することが大切です。
代表的に避けたほうが良いのは、刃物類です。包丁やナイフは「縁を切る」という意味合いがあるため、夫婦の門出を祝うシーンには不向きです。
次に、ガラスや陶器などの割れ物も注意が必要です。「割れる」=「別れ」や「壊れる」を連想させるため、特に目上の方やフォーマルな場では控える方が安心です。
また、ハンカチは「涙を拭く」と連想されることがあり、祝い事には不適切とされることがあります。さらに、香りが強すぎるアロマや派手な装飾品も好みが分かれるため、無難に避けた方が良いでしょう。
ただし相手が希望すれば贈っても大丈夫です。贈答品の中でも高級な包丁やグラスや陶器は人気商品でもあるのですよね。
親しい間柄で贈り物には何が良いかを聞いたときにこれらの商品を希望されたら贈ってもかまいません。ただしグラスなどを贈るときは数も重要です。
本来割り切れる数はNGとも言われますが、ペア(2)や半ダース(6)、1ダース(12)、末広がり(8)は偶数であっても一組として考えるので贈っても大丈夫です。
4は(死)を連想させるので避けます。また奇数でも9は(苦)を連想させるので避けます。
結婚祝いは特に、見た目の華やかさだけでなく、意味やマナーも考慮することが、相手に喜ばれるポイントです。
新築・開店祝いでNGとされる贈り物
親しい人が家を新築したりお店を開店したときにはお祝いのプレゼントを贈る場合もあると思いますが、贈り物選びに少し注意が必要です。
まず避けたいのは、火や赤いもの。キャンドルや赤い装飾品は「火事」を連想させるため、縁起を重んじる場では控えた方が安心です。
新築の家やこれから開業するお店というのはそれまでに努力を重ねてたどり着いた結晶ですから、すべて燃えてしまう火事を連想させてはお祝いの席も台無しになってしまいます。
次に、割れやすい陶器やガラスの置物も注意点です。「割れる」=「破損・不運」のイメージがあるため、祝いの場には適しません。
また、香りが強いアロマや手入れが必要な植物も、相手の負担になることがあるため避けた方が無難です。
また絵画や壁掛け時計などは、お洒落なインテリアになるのでお祝いとして人気な品物なのですが、最近の住宅では不向きだとも言われています。
なぜかというとこれらを壁に飾るときには壁に穴を開ける必要があるからです。最近のマンションなども壁に穴を開けないように限られた設置スペースが設けられている場合が多いのです。
おすすめは、縁起の良い観葉植物や、実用的で長く使える雑貨です。開店の祝い酒には日本では日本酒が祝い事のお酒として贈られます。祝い事には奇数が吉とされるのですが、日本酒では一升瓶が2本一対がおめでたい席での本数です。ただし4本はタブーです。
贈る際には包装やのし紙を丁寧にすると、相手に対する配慮が伝わり、安心して喜んでもらえる贈り物になります。
▼関連記事▼
長寿の祝い・退職祝いの贈り物のタブー
お祝いに現金を贈る場合がありますが、実は目上の人に対しては現金はタブーだとされています。長寿の祝いや退職祝いなどには現金ではなく品物や商品券を贈るようにします。
他にも目上の人には贈っては失礼だとされているものに「靴」「靴下」「スリッパ」があります。これは踏みつけるというイメージから言われるものです。
他にも「勤勉」という意味にあたる「カバン」や「時計」も贈り物には相応しくありませんので注意しましょう。
お中元・お歳暮の注意ポイント
お中元やお歳暮は季節の挨拶として贈ることが多いですが、マナーとして避けたい品物や数字にも注意が必要です。
まず、縁起の悪い数字は控えましょう。「4(死)」「9(苦)」は縁起が悪いとされるため、ギフトセットや包装に入っていないか確認すると安心です。さらに、足元に関連するものやハンカチ、金券などは、贈る相手や地域によっては失礼に当たることがあります。
また、賞味期限や消費期限が極端に短い食品は、相手に迷惑をかける可能性があるので注意しましょう。
お中元やお歳暮は、相手の生活や好み、地域の習慣を考慮した上で、無難で喜ばれる品を選ぶことが、失礼なく心遣いを伝えるコツです。
▼関連記事▼
お見舞いにふさわしくない贈り物
親しい人が入院したときのお見舞いの品は何を贈ってよいのか迷ってしまいますね。お見舞いでの贈り物は、相手の体調や環境に配慮することが何より大切です。
避けたいのは、鉢植えの植物や枯れやすい花。手入れが大変で相手に負担をかける可能性があります。花持ちが良いからといえ鉢植えの花は「根付く」から「寝つく」を連想させるのでお見舞いにはタブーです。
逆に、切り花や長持ちする観葉植物、小さなお菓子や果物など、手軽に楽しめるものが喜ばれます。ただし、たとえ相手が真紅のバラが好きでも真っ赤な花は血を連想させるのでお見舞いにはNGです。他にもツバキのような首が落ちる花や弔事に用いられる白い花も避けてください。
また、香りの強すぎるアロマやスパイス、派手な装飾品も、体調や好みによっては不快感を与えることがあります。
さらに、食品を贈る場合は賞味期限が長く、消費しやすい量を意識すると安心です。
お見舞いは相手を気遣う気持ちを伝える場。意味や見た目よりも、相手が安心して受け取れるかどうかを優先することが、心のこもった贈り物選びのポイントです。
▼関連記事▼
知っておくと安心!スマートな贈り方のコツ

贈り物は、品物やタブーを押さえるだけでなく、相手の範囲や心遣いを意識することで、より印象の良い贈り物になります。
どんなに素敵な品でも、相手との関係性や贈るシーンに合っていなければ、気持ちが十分に伝わりません。ここでは、贈る相手に喜んでもらうためのちょっとした工夫や、スマートに渡すコツを具体例とともにわかりやすく解説します。
心を伝えるメッセージの書き方
贈り物には品物だけでなく、手書きのメッセージを添えると、気持ちがより伝わります。たとえば結婚祝いなら「お二人の幸せを心から願っています」、お見舞いなら「一日も早い回復をお祈りしています」といった具体的で温かい言葉が喜ばれます。
メッセージカードはシンプルで読みやすいものを選び、丁寧な字で書くことがポイントです。文章の長さは短すぎず長すぎず、気持ちが自然に伝わる適度なボリュームにまとめましょう。
さらに、相手との関係性に応じてユーモアや思いやりを加えると、より印象に残る贈り物になります。品物とメッセージの組み合わせで、贈る側の心遣いがしっかり伝わるのが魅力です。
金額やのし袋のマナー
贈り物の金額やのし袋の使い方も、マナーとして押さえておくことが大切です。
一般的には、結婚祝いは相場3,000〜10,000円、お中元・お歳暮は3,000〜5,000円が目安です。目上の方や特別な相手には、少し高めの金額設定でも問題ありません。
また、のし袋は贈るシーンに応じて種類や表書きを使い分けます。結婚祝いは「寿」、お見舞いは「御見舞」、出産祝いは「御祝」と明記すると丁寧です。表書きは毛筆や筆ペンで書くと、より格式が出て好印象になります。
贈る側の気持ちを示す金額のバランスや適切な包装が、失礼のないスマートな贈り物のポイントです。
お祝いの贈り物は誰まで贈る?
贈る相手の範囲もマナーの重要な一部です。親族は近しい関係なら必ず贈るのが基本ですが、友人や知人の場合は、親しい関係かどうかを基準に考えるのが自然です。
職場の場合は、直属の上司やチーム単位で贈ることが多く、社内ルールや関係性を確認してから行うのが安心です。
また、範囲を間違えると、相手や周囲に気まずさを与える場合があります。特に家族や職場など、人間関係の距離感を意識した判断が大切です。
贈る相手を適切に選び、タイミングや渡し方と組み合わせることで、よりスマートで印象の良い贈り物になります。
マナーを守りながら喜ばれる贈り物を選ぶコツ
贈り物はマナーを守ることも大切ですが、最も大事なのは相手が喜ぶかどうかです。相手の好みや生活スタイルに合わせて品物を選ぶことで、形式的なタブーを柔軟に考えられます。
ここでは、心を伝えるメッセージや相手目線を意識した贈り方のポイントを具体例とともに紹介します。
相手目線を最優先に考える
贈り物を選ぶときは、まず相手が本当に喜ぶかどうかを基準にすることが大切です。たとえば、煎茶は弔事のイメージが強いため結婚祝いには不向きと言われますが、相手が好む品であればポジティブな意味で贈ることもできます。
大切なのはマナーやタブーだけにとらわれず、相手の趣味や生活スタイルに合ったものを選ぶことです。また、相手の立場や年齢、関係性に応じて柔軟に対応することもポイントです。
たとえ一般的にはタブーとされる品物でも、親しい関係であればユーモアや思いやりを添えて贈ることで、かえって喜ばれる場合もあります。贈り物は「マナー」と「気持ち」のバランスが大切。相手目線を意識することで、より心に残る贈り物になります。
タブーも柔軟に対応する
贈り物のタブーは、状況や相手によって柔軟に考えることが大切です。例えば、刃物も通常は「縁を切る」として避けられますが、相手との関係性や贈る意味付け次第で、「未来を切り開く」 という前向きなメッセージとして贈ることも可能です。
また、地域や文化によって避ける品や数字は異なるため、相手の慣習や好みに応じて判断することが重要です。
つまり、形式的なルールだけでなく、贈る側の思いや気持ちをどう伝えるかが、タブーを乗り越える鍵となります。
相手に喜んでもらうことを最優先に、柔軟かつ丁寧に贈り物を選ぶことが、マナーを守ったスマートな贈り方のポイントです。
風呂敷包みで丁寧さを伝える
目上の方に贈る場合やフォーマルなシーンでは、風呂敷で包むことが贈り物の印象を大きく変えます。
風呂敷で包むことで、丁寧さや心遣いが自然と伝わり、贈る側の誠意を示すことができます。さらに、風呂敷は包み方次第で形や大きさを調整できるため、どんな形状の品物にも対応可能です。
また、風呂敷は再利用できるため、環境にも優しい贈り方として注目されています。包装紙や紙袋だけでは伝えきれない細やかな配慮や美意識を、風呂敷を使うことでプラスできるのが魅力です。
贈り物の内容だけでなく、包み方にも気を配ることで、より印象の良い贈り物になります。
まとめ
贈り物は、品物選びだけでなくタイミングや渡し方、相手の範囲まで考えることで、より気持ちが伝わるものになります。
タブーや避けるべき品を押さえつつ、相手目線で選び、スマートに渡すことで、贈る側も受け取る側も気持ちよくなれます。
この記事のポイントを参考に、失敗のない贈り物で、日常のちょっとした喜びや大切な節目を、より素敵なものにしてください。
▼関連記事▼