お盆が過ぎても暑さが続く日本の夏。そんな時期に相手の体調を気づかう「残暑見舞い」は、ちょっとした心配りとして喜ばれるごあいさつです。
でも、「いつまでに出すのが正解?」「暑中見舞いと何が違うの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、残暑見舞いの出す時期の目安やマナー、書き方のコツに加え、送る相手に合わせた文例や、ちょっと気の利いたアイデアまでわかりやすくご紹介します。
残暑見舞いはいつまでに出す?時期の目安をチェック
残暑見舞いはいつまでに出せばよいのか、毎年タイミングに迷う方も多いですよね。立秋から処暑の頃までが一般的な時期とされますが、地域差や遅れて出す場合のマナーも知っておきたいところ。
暑中見舞いとの違いを踏まえ、気持ちがしっかり届くよう、出すタイミングや表現の工夫についてもわかりやすく解説します。
残暑見舞いを出す期間の目安
残暑見舞いって、いつ出せばいいの?と毎年ちょっと迷ってしまいますよね。基本的には、立秋(8月7日ごろ)を過ぎてから、暑さが残る時期に送るご挨拶が「残暑見舞い」です。
出す時期の目安は 立秋〜8月末ごろまで。それまでは「暑中見舞い」、立秋以降は「残暑見舞い」となります。
ただ、地域や年によっては9月に入っても真夏のような気温が続くこともあり、「残暑見舞い」の時期も少し伸びている傾向にあります。
とはいえ、形式としては 8月中に届くように出すのが無難。あまり遅くなると時期外れの印象を与えてしまうことも。目安としては「お盆を過ぎたら早めに書く」がちょうどよいタイミングです。
ちょっとした近況報告や、相手の体調を気づかうひと言を添えると、ぐっと温かい印象に。季節の挨拶って、意外と心に残るものなんです。
9月に入ってもOK?遅れても気持ちが伝わるひと工夫
うっかり残暑見舞いのタイミングを逃してしまった…そんなときは、9月上旬までであればまだ挽回のチャンスあり!最近では暑さが長引くこともあり、「季節の挨拶」として9月頭に出しても違和感は少なくなっています。
ポイントは、「遅れてしまったことを素直に伝える」こと。たとえば文面の最初に、「ご挨拶が遅くなってしまいましたが…」「9月に入りましたが、まだまだ暑さが続いていますね」といったひと言を添えるだけで、印象がグッと良くなります。
また、相手の健康や近況を気づかう言葉をしっかり入れれば、単なる形式的なハガキではなく、「気にかけてくれているんだな」という温かさが伝わりますよ。
形式にとらわれすぎず、“ちょっとした思いやり”を大切にすれば、残暑見舞いは9月に入ってからでも十分に心のこもった挨拶になります。
残暑見舞いってどんなもの?暑中見舞いとの違い

暑中見舞いと残暑見舞い、似ているようで実は意味や送る時期に違いがあります。どちらも夏のごあいさつですが、使い分けのポイントを知らないと失礼になることも。
言葉の選び方や、時期によるニュアンスの違いについて丁寧に説明し、これからの季節に役立つ基礎知識をまとめました。
残暑見舞いとは?気持ちを伝える夏のごあいさつ
残暑見舞いとは、立秋(例年8月7日ごろ)を過ぎたあとに出す季節のあいさつ状のこと。
暑さが続く中で「お体を大切にしてくださいね」という気遣いや、日頃の感謝を伝える役割があります。ビジネス・プライベート問わず、ちょっとした心づかいを形にできる日本ならではの習慣です。
もともとは、夏の暑さで体調を崩しやすい時期に、直接お見舞いに行けない相手を気づかうために生まれた風習。それが手紙やハガキの形に変わり、現在の「残暑見舞い」となっています。
今ではメールやLINEでカジュアルに送る人も増えていますが、やっぱりハガキやカードのほうが印象に残りやすく、丁寧な印象を与えることができます。
暑中見舞いとの違いは?出す時期と気温だけじゃない
残暑見舞いと暑中見舞いの大きな違いは、「出すタイミング」にあります。
暑中見舞いは梅雨が明け、本格的な夏の到来を感じる頃(小暑〜立秋の前日まで)に出すのに対し、残暑見舞いは立秋を過ぎたあと、まだ暑さが続いている時期に出します。
でも違いはそれだけではありません。暑中見舞いは「これから夏本番ですね、お体に気をつけて!」という前向きなニュアンスが強いのに対し、残暑見舞いは「猛暑が続いていますね、お疲れが出ていませんか?」と、やや労わり寄りの表現が中心になります。
文面も、暑中見舞いが“元気づけ”なら、残暑見舞いは“ねぎらいと感謝”がベースになる、といったイメージです。
季節のあいさつは細やかな気づかいが伝わるチャンス。タイミングや言葉選びを少し意識するだけで、グッと好印象につながります。
残暑見舞いの書き方とマナー
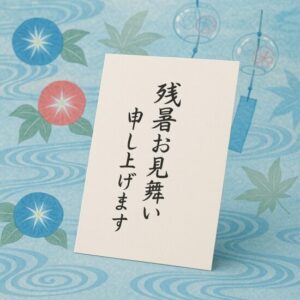
残暑見舞いを出すときの基本的な書き方や、よく使われる例文、添えると印象がよくなるひと言などを紹介します。手書きでもメールでも失礼のない伝え方を知って、相手に気持ちよく届く残暑見舞いにしましょう。
基本的な文例と使える言い回し
残暑見舞いの文章は、かしこまりすぎず、でも失礼のないように書くのがポイントです。相手との関係性や、送るシーンに合わせて、言葉選びを工夫しましょう。
たとえば、フォーマルな関係や目上の方にはこんな一文が使えます
「残暑の折、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」「厳しい暑さが続いておりますが、どうかご自愛くださいませ。」
一方、親しい友人や同僚など、カジュアルな関係では少しくだけた表現もOK。
「まだまだ暑いね。体調崩してない?」「夏の疲れが出やすい時期だから、無理しないでね!」
また、家族宛てや久しぶりに連絡する人には、近況報告を入れると親しみやすくなります。
「こちらはなんとか元気にやっています。」「○○さんもお変わりありませんか?また落ち着いたら会いましょう!」
書き出しのあいさつに「残暑お見舞い申し上げます」と入れたうえで、暑さをねぎらい、相手の健康を気づかう文面にすると、気持ちが伝わります。
短くても「心を込めたひとこと」があると印象が変わるもの。決まり文句に頼りすぎず、自分の言葉でまとめてみてくださいね。
ハガキ?メール?どちらがいい?
残暑見舞いといえば、昔ながらのハガキを思い浮かべる方も多いですよね。でも、今はメールやLINEで送る人も増えています。どちらが正解、というよりは、相手との関係性やシーンに合わせて選ぶのが自然です。
まず、ハガキの魅力はやはり「丁寧さ」と「季節感」。特に目上の方やビジネス相手、お世話になった方には、ハガキで出すと気持ちがしっかり伝わります。手書きで一言添えると、ぐっと温かみが増します。
一方で、メールやLINEなどのデジタルツールは、気軽に送れるのが利点。たとえば忙しい毎日のなかでも、すぐにメッセージを届けられるので、友人や家族、同年代の人にはこちらでも十分気持ちが伝わります。
最近は、スマホで作れる「オンラインハガキ」も人気。ハガキのような形式で、ネットから気軽に送れて便利です。
年代によっても好まれるスタイルは違ってきます。年配の方にはハガキ、若い世代にはメールやSNSがなじみ深いことも。迷ったときは「どんなふうに受け取ってもらえたらうれしいか」をイメージして選ぶと失敗しません。
「カタチ」にとらわれすぎず、大切なのは「相手を気づかう気持ち」。あなたらしいスタイルで、季節のごあいさつを届けてみてくださいね。
送る相手別・おすすめの残暑見舞いアイデア
残暑見舞いは送る相手によって言葉選びやトーンが変わります。家族や親しい友人には親しみのこもった一言を、ビジネス相手や目上の方には失礼のない丁寧な表現を選びたいですね。
シーン別・相手別に適した文例や、気持ちが伝わるちょっとした工夫、印象を良くするアイデアもご紹介します。
上司・取引先には?フォーマルだけど気の利いた文面に
目上の方やビジネス相手には、やはり形式を重んじつつも、少し心が和むような文面が好まれます。
たとえば「ご自愛ください」などの表現はよく使われますが、それだけでなく、相手の業種や仕事状況に合わせて一文添えると印象がアップします。
例:「猛暑の折、ご多忙のことと存じますが、何卒ご自愛専一にてお過ごしください。」
堅すぎず、でも軽すぎない、このバランス感が大切です。オリジナルの一言を加えるだけで、「ちゃんと考えてくれているな」と感じてもらえます。
友人・家族には?カジュアルで心が近づく一言を添えて
親しい人には、ちょっとした近況やユーモアを交えた言葉もOKです。「アイスばっかり食べてるよ〜」とか「涼しくなったら会おうね」など、会話調の一文を入れるだけでグッと親しみが増します。
家族には、「体調くずしてない?」「クーラー使いすぎてない?」など、気遣いが伝わる言葉を。ハガキでもLINEでも、相手との関係性に合った自然な言葉選びがコツです。
残暑見舞いに添えたい、ちょっとした気遣いアイテム
残暑見舞いは文字だけのご挨拶でも十分ですが、そこに“ちょっとした気遣い”を添えることで、ぐっと心の距離が縮まります。
特に暑さが長引くこの時期は、ひんやり感や癒しを感じられるアイテムが喜ばれます。封書にできる範囲のプチギフトで、さりげない思いやりを伝えてみませんか?
受け取ってうれしい!涼やか&実用的なアイデア
-
冷感アイテム
ミニサイズの冷却シートやおしぼりタオル、ポケットサイズの冷感ミストなどは、使い勝手も良く、ちょっとしたお礼にもぴったり。デザインが和風や夏仕様だと、さらに季節感もアップ。 -
涼しげなお菓子や飲み物
常温保存できるゼリー、寒天スイーツ、ひとくちサイズの水ようかんなども人気。ティーバッグタイプの冷茶やノンカフェインハーブティーなども、健康を気づかう気持ちが伝わります。 -
香りや癒しのグッズ
アロマ付きのしおり、お香のミニサンプル、夏の香りがする文香(ふみこう)などもおすすめ。メッセージカードに香りをつけて送るだけでも、印象に残ります。
📮 プチメモ:
ハガキではなく封書で送ると、厚みのあるアイテムも同封できます。送料やサイズ制限には注意しましょう。
シーン別・おすすめの添え方と注意点
-
ビジネス相手には
華美な贈り物は避け、上質な茶葉や涼感タオルなど控えめで実用的なものを。手書きの一言があると、好印象です。 -
高齢の親族や目上の方には
冷たい麦茶やノンカフェインのお茶、塩分補給ができる飴など、健康を気づかうものを選ぶと安心感があります。 -
友人や同僚には
パッケージがかわいい夏のお菓子や、プチプラのコスメサンプルなど、話題のアイテムも◎。相手の趣味に合えば、LINEギフトもアリ。 -
注意点としては…
食べ物や香りアイテムを送るときは、相手の好みやアレルギーへの配慮を忘れずに。あくまで“ちょっと添える”がポイントです。
まとめ
残暑見舞いは、立秋を過ぎた晩夏に、相手を思いやる気持ちを届けられる素敵な習慣。時期やマナーをおさえれば、より丁寧な印象を与えられます。
文例やプチギフトの工夫を取り入れて、自分らしい残暑見舞いを楽しんでみてはいかがでしょうか? 忙しい毎日だからこそ、ふと心がほどけるような一通を贈ってみましょう。





















